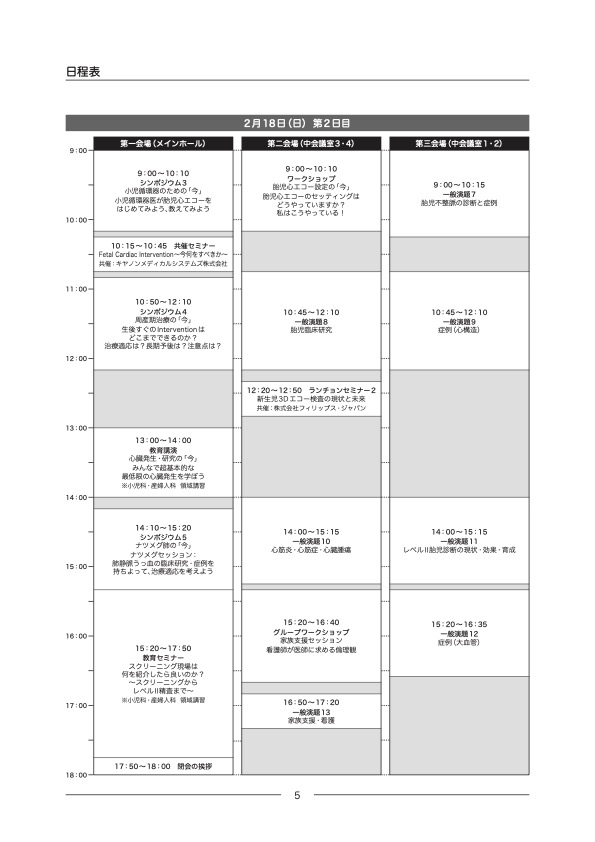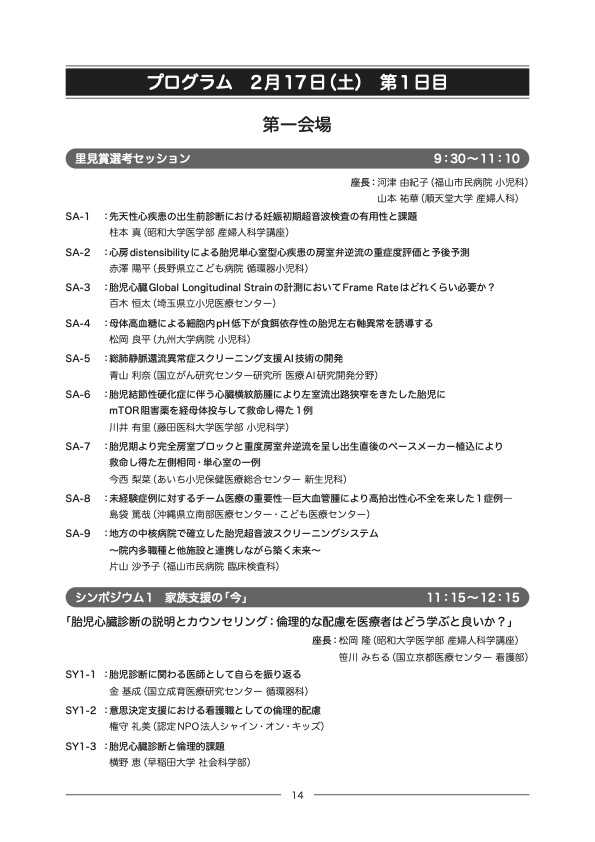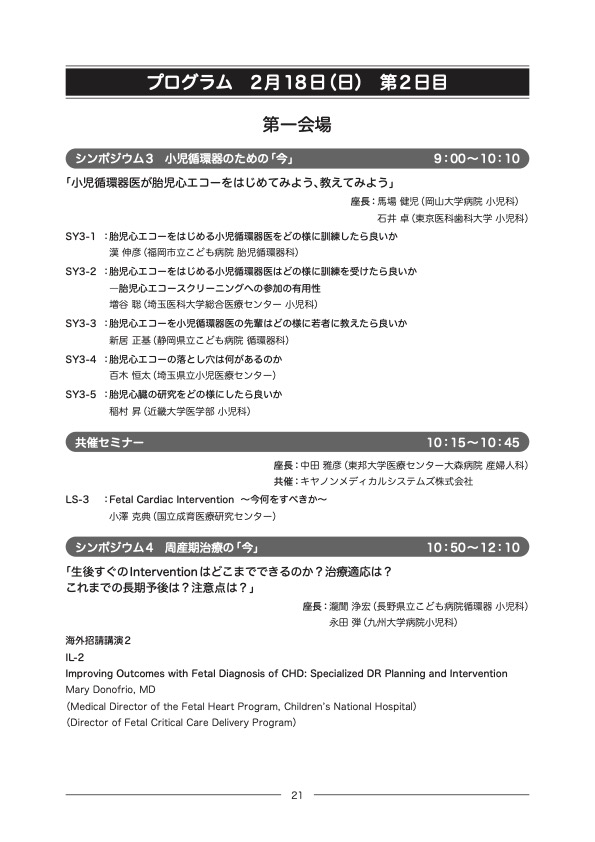プログラム・日程表
─ 日程表 ─
─ 演題・プログラム詳細 ─
注目セッション
海外招請講演
Dr Mary Donofrio, MD
ワシントン大学教授
アメリカFetal Heart Society 初代理事長

特別講演
里見元義 先生
日本胎児心臓病研究会 初代代表幹事
「胎児心臓病学の原点」
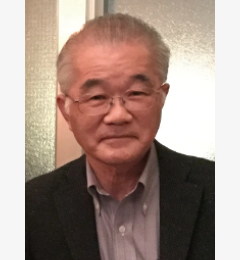
シンポジウム(第一会場:メインホール)
シンポジウム1「家族支援」の今
2月17日(土) 11:15 〜 12:15
胎児心臓診断の説明とカウンセリング
倫理的な配慮を医療者はどう学ぶと良いか?
シンポジウム2「日本の胎児心臓」の今
2月17日(土) 15:15 〜 17:05
胎児心臓の連携は地域ごとでどうなっているのか?
現状と課題を共有しよう
シンポジウム3「小児循環器のため」の今
2月18日(日) 11:15 〜 12:15
小児循環器医が胎児心エコーをはじめてみよう、教えてみよう
シンポジウム4「周産期治療」の今」の今
2月18日(日) 10:50 〜 12:10
生後すぐのInterventionはどこまでできるのか?
治療適応は?長期予後は?注意点は?
シンポジウム5「ナツメグ肺」の今
2月18日(日) 14:10 〜 15:20
ナツメグセッション:
肺静脈うっ血の臨床研究・症例を持ちよって、
治療適応を考えよう
教育講演・教育セミナー(第一会場:メインホール)
教育講演「心臓発生・研究」の今
2月18日(日) 13:00 〜 14:00
みんなで超基本的な最低限の心臓発生を学ぼう

山岸敬幸先生

八代健太先生
教育セミナー
2月18日(日) 15:20 〜 17:50
スクリーニング現場は何を紹介したら良いのか?
〜スクリーニングからレベルII精査まで〜?
Normal variantの胎児心臓 武井 黄太先生(長野県立こども病院循環器小児科)
Borderlineの胎児心臓 石井 陽一郎先生(大阪母子医療センター小児循環器科)
胎児の心外異常 新谷 光央先生(静岡県立こども病院産科)
胎児心臓の心拍数・リズム 前野 泰樹先生(聖マリア病院新生児科)
ジョイントセッション・ワークショップ・共催セミナー
JSE/JSFCジョイントセッション
2月17日(日) 14:10 〜 15:10
「ストレイン」の今
第一会場(メインホール)
ワークショップ
2月18日(日) 9:00 〜 10:10
「胎児心エコー設定」の今
第二会場(中会議室3・4)
グループワークショップ
2月18日(日) 15:20 〜 16:40
胎児心看護師が医師に求める倫理観
第二会場(中会議室3・4)
共催セミナー
その他、一般演題多数
皆さんと胎児心臓の「今」を考えましょう